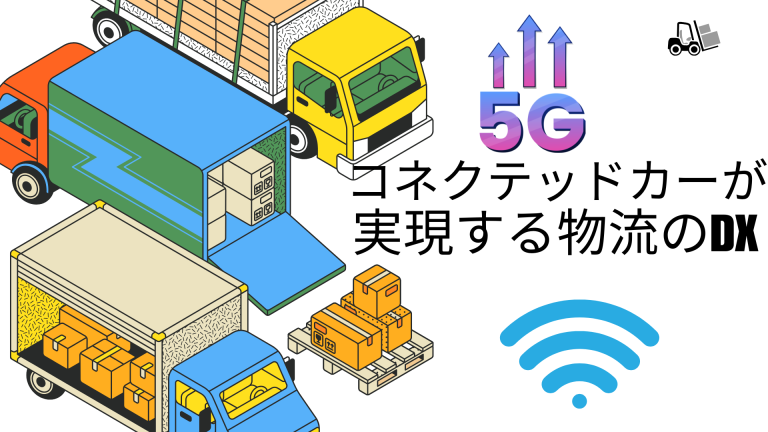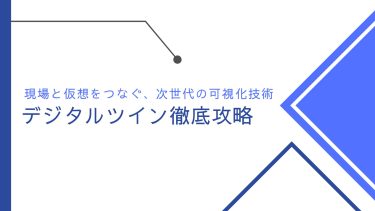「物流の2024年問題」が叫ばれて久しいですが、ドライバー不足や燃料費の高騰といった課題は、今なお多くの物流事業者様にとって深刻な経営課題となっています。日々の業務に追われ、対策を打ちたいと思っても、何から手をつければ良いのかわからないという法人は多いのではないでしょうか。
その解決の鍵を握るのが、「物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)」であり、その中心的な役割を担うのが「コネクテッドカー」です。
この記事では、コネクテッドカーが物流をどう変えるのか、その具体的な活用法から、コストの抑え方、そして国の補助金制度まで、中小企業の目線で分かりやすく解説します。
「コネクテッドカー」とは?

まずは、「コネクテッドカー」について簡単に解説します。言葉としては難しく聞こえてしまうかもしれませんが本質的な意味を解説することで、これまでの車との決定的な違いをはっきりさせていきます。
OTAが常識に。ソフトウェアで進化する車
「コネクテッドカー」とは、一言でいえば「インターネットに常時接続する機能を備えた車」です。
私たちが持っているスマートフォンは、購入後もソフトウェア・アップデートによって新しい機能が追加されたり、セキュリティが強化されますが、これと同じことが、車で起きます。
コネクテッドカーは「購入後も進化し続ける」製品(まさしくスマートフォン)と言えます。
例えば、無線通信でソフトウェアを更新するOTA(Over-the-Air)技術により、新しいナビ機能が追加されたりする時代が来ています。
この「つながることで進化する」という概念こそが、コネクテッドカーの本質です。
コネクテッドカーを構成する4つの構成要素
「コネクテッドカー」は、主に4つの技術要素が連携することで成り立っています。
1.車両制御技術
車の「走る・曲がる・止まる」を電子的に制御する基盤技術です。自動ブレーキや車線維持支援などがこれにあたります。
2.情報通信技術(ICT)
5G/LTEといったモバイル通信網やGPSなどを使い、車と外部サーバーとの間でデータをやり取りする技術です。この記事のメイントピックです。
3.データ分析・活用技術
車両から集められた膨大な情報(ビッグデータ)を蓄積し、AI(人工知能)などを用いて分析・解析する技術です。
4.サービス提供基盤
分析されたデータを基に、交通情報配信や車両管理システム、エンターテイメントなど、ドライバーや管理者に有益なサービスを提供するアプリケーション部分です。
これらが一体となって機能することで、「コネクテッドカー」は新たな価値を生み出すプラットフォームとしての役割を担います。
なぜ、「コネクテッドカー」は物流業界で注目されているのか。
ここまでは「コネクテッドカー」について解説してきました。
では、この「コネクテッドカー」がなぜ物流業界からの熱い注目を浴びているのでしょうか。
この理由については業界が直面する深刻な問題が関係しています。
物流業界が抱える問題を「コネクテッドカー」がどのように解決していくかを解説していきます。
物流業界が直面する深刻な課題

コネクテッドカーが必須科目となりつつある背景には、避けては通れない深刻な課題があります。
・2024年問題と人手不足の深刻化
働き方改革関連法によってドライバーの時間外労働に上限が課せられました。
これにより、一人のドライバーが運べる量が減少し、物流業界全体の売上減につながるだけでなく、ドライバー自身の収入減による離職を加速させる懸念も指摘されています。
・コスト構造の圧迫
軽油価格の高騰は輸送コストに直結します。さらに、タイヤなどの部材費、人件費、車両維持費も上昇傾向にあり、利益の確保が年々難しくなっています。
・個人宅への配送の急増
通販会社の発達やコロナ禍の外出自粛等の影響で、小口配送が急増しています。これにより在庫管理の複雑化等が起き、業務全体の効率が悪くなってしまいます。
コネクテッドカーが注目される理由
「2024年問題と人手不足の深刻化」「コスト構造の圧迫」「個人宅への配送の急増」
これらの問題に対しての解決方法として期待されているのが「コネクテッドカー」です。
それぞれの問題に対して以下のようなメリットをもたらします。
1.2024年問題と人手不足の深刻化
・運用効率化
⇒車両データを活用した最適ルート提案や渋滞回避により、同じ時間内の配送件数を増やす。
・動態管理による稼働率向上
⇒リアルタイムで車両位置や稼働状況を把握し、空き車両の有効活用や積載量の最大化が可能。
2.コスト構造の圧迫
・燃費改善
⇒走行データから無駄なアイドリングや急加速を減らし、燃料コストを削減。
・効率的な配車
⇒AIによる配送計画最適化で、走行距離を削減し、燃料と時間コストを圧縮。
3.個人宅への配送の急増
・ラストワンマイル最適化
⇒配送先情報をリアルタイムで更新し、効率的なルート選定。置き配や再配達削減につながる。
・リアルタイム通知
⇒顧客に到着予定を自動通知し、受け取り率を向上。再配達を減らす。
このように、コネクテッドカーは、データ活用により物流業界の問題に対して改善策をもたらします。
コネクテッドカーはこれから物流業界に対して必須な存在となっていくでしょう。
物流DXとは

「物流DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、AI・IoT・ビッグデータ・自動運転などのデジタル技術を活用し、物流の業務プロセスやビジネスモデルを根本から変革する取り組みのことです。
この取り組みは物流業界における問題を解決し、持続的な物流を実現する鍵となります。
しかし、物流DXは単なるデジタルツールの導入(デジタイゼーション)ではありません。
物流DXを理解するためにはデジタル化への3つのステップを把握することが重要です。
1.デジタイゼーション
紙の地図をナビアプリに、紙の日報をExcelに変えるといった「アナログからデジタルへの置き換え」の段階のことを言います。
2.デジタライゼーション
ナビアプリと動態管理システムを連携させ、配送プロセス全体をデジタルで管理・効率化する段階のことを言います。
3.DX(デジタルトランスフォーメーション)
収集した走行データなどを分析することで新たな配送サービスを創出したり、荷主に対して付加価値の高い物流提案を行ったりすることで、事業モデルそのものを変革し、新たな競争優位性を確立します。
つまり、物流DXとは単なるIT化ではなく、デジタルの力で物流ビジネスを進化させる取り組みだと言えます。
コネクテッドカーは、この3段階すべてに貢献し、特に「DX」を実現するための強力なエンジンとなります。
導入のメリット
ここでは「コネクテッドカー」を導入することによって期待されるメリットについて解説していきます。
メリットにつきましては以下の4つです。
- 生産性の向上とコスト削減
- 安全性の向上と事故リスクの低減
- ドライバーの労働環境改善と定着率向上
- 顧客満足度の向上と新たな価値創出
これらの視点から解説していきます。
生産性の向上とコスト削減
AIによる最適ルート案内で配送時間を短縮することで燃料費を削減することが可能です。
また、運動日報の自動作成を行うことで、ドライバーの事務作業を減らすことも可能です。
さらに、車両の稼働状況を正確に把握することで、無駄なアイドリングの削減や実車率(荷物を積んで走行している割合)の向上にもつながります。
安全性の向上と事故リスクの低減
急ブレーキや急ハンドルといった危険運転をデータで検知し、個々のドライバーに合わせた具体的な安全指導が可能になります。ドライブレコーダーと連勤すれば、事故発生時の状況証拠を保全し、原因究明や保険会社とのやり取りをスムーズに進められます。
ドライバーの労働環境改善と定着率向上
長時間労働の是正や事務作業の削減は、ドライバーの心身の負担を軽減します。また、客観的なデータに基づく公正な評価制度を構築しやすくなり、従業員満足度の向上と人材の定着に貢献します。
顧客満足度の向上と新たな価値創出
荷物の正確な到着予定時刻を荷主に共有したり、温度管理が必要な荷物の輸送品質をデータで証明したりすることで、顧客からの信頼を高めます。
注意すべきデメリットと対策
メリットがある一方で懸念されるデメリットもあります。このデメリットについて3つの点から解説していきます。
デメリットは以下の3つです。
- 導入・運用コスト
- セキュリティリスク
- 通信環境への依存
これらの点から対策方法も交えて解説していきます。
導入・運用コスト
車両への専用端末の設置や、システム利用料といったコストが発生します。
【対策】
国の補助金(IT導入補助金、中小企業省力化投資補助金など)を利用することで初期投資を抑えることが可能です。また、システム利用料においては格安SIM(MVNO)を利用することで費用を抑えることが可能です。
格安SIM(MVNO)については以下の記事で解説しているのでぜひご参照ください。
セキュリティリスク
車両がインターネットにつながるということは、サイバー攻撃の標的になる可能性もゼロではありません。
【対策】
セキュリティ対策が施された信頼性の高いシステムや通信サービスを選ぶことが極めて重要です。
通信環境への依存
山間部など、電波の届きにくい場所ではデータが取得できない可能性があります。
【対策】
広範囲なエリアや最適なエリアをカバーする通信キャリアを利用したSIMサービスを選ぶことが有効です。
未来の物流を支える「IoT」「5G」「AI」の役割
コネクテッドカーという「体」を動かすためには、情報を集める「神経」と、それを伝える「伝達経路」、そして全体を制御する「脳」が必要です。このセクションでは、その重要な役割を担う「IoT」「5G」そして「AI」という3つのテクノロジーについて、それぞれの機能と連携を深掘りします。
IoTとは?~トラックの隅々まで”神経”を通わせる技術~
IoTの役割は、これまでブラックボックスだった車両や輸送の状況を、データとして可視化することです。具体的には以下のようなデータを収集します。
・CAN(Controller Area Network)データ
車両の電子制御ユニット(ECU)間を流れる内部データ。エンジン回転数、燃料消費量、アクセル開度、ブレーキの踏み込み具合、シートベルトの着用状況など、非常に詳細な車両情報が取得できます。
・プローブ情報
GPSから得られる位置情報(緯度経度)、速度、時刻といった走行軌跡データのことを言い、動態管理やルート分析の基礎となります。
・センサーデータ
ドライブレコーダーの映像や加速度センサーによる衝撃検知データや荷台に取り付けた温度・湿度センサーのデータなどの後付けの機器から得られる情報です。
IoTは、これらのデータを収集する「神経網」として機能し、あらゆる事象を客観的なデータに変換します。
IoTについては以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご参照ください。
また、物流業界におけるIoTの導入事例についても解説しているのでこちらもぜひご参照ください。
5Gとは?~神経網を流れる情報を送る”伝達経路”~
5Gは、IoTで集めた膨大なデータを送受信するための第5世代移動通信システムです。その特徴は、物流DXを加速させる3つの要素に集約されます。
・超高速・大容量
ドライブレコーダーの高精細な映像データや、車両全体のセンサーデータをリアルタイムでクラウドにアップロードすることができます。また、事故発生時だけでなく、平常時の運転状況を映像で確認することも容易になります。
・超低遅延
通信のタイムラグがとても小さいため、遠隔地からの建機やトラックのリアルタイム操縦や、後述する隊列走行において、極めて安全で正確な車両制御が可能になります。
・多数同時接続
1平方キロメートルあたり100万台もの機器を同時に接続できます。
将来的にはトラックだけでなく、個々のパレットやコンテナに取り付けられることで膨大な数の「モノ」が同時に情報を発信することが期待されています。このようにして5Gは物流社会の基礎となります。
AIとビックデータの役割~集めたデータを「価値」に変える”脳”~
コネクテッドカーはデータを集めるだけでは意味がありません。収集された膨大なデータを分析し、未来予測や最適化といった「価値ある情報」に変換する役割を担うのがAI(人工知能)です。
AIは、いわば物流DXの「脳」として機能します。
・予測
過去の走行データと天候、曜日の傾向などを分析し、「この先のルートで渋滞が発生する確率」や「ルート先における事故情報」などを予測・先取します。
・最適化
その日の荷物の量、配送先の位置、時間指定、ドライバーの労働時間といった複雑な条件をすべて考慮し、全車両の最も効率的な配送計画を瞬時に計算します。
・認識
ドライブレコーダーの映像を解析し、わき見運転や居眠りといったドライバーの危険な状態や、一時不停止などの交通違反を自動で認識し、警告を発します。
IoTが「神経」、5Gが「伝達経路」、そしてAIが「脳」。この3つが連携することで、コネクテッドカーは真価を発揮するのです。
【事例でわかる】コネクテッドカー活用イメージ

ここまでの技術解説を踏まえて、物流現場における具体的な活用イメージについて解説していきます。
また、解説していく事例を支える「SIMカード」についても解説していきます。
すべての活用例を支える「SIMカード」の存在
これから紹介する活用例は、トラックと事務所(クラウドサーバー)の間で、インターネットを通じてリアルタイムに「情報をやり取り」することで成り立っています。
そして、その安定した情報の通り道を確保しているのがトラックに搭載された専用端末やドライブレコーダーに挿入されたSIMカードです。
コネクテッドカーの導入効果は、SIMカードの運用方法に大きく左右されると言えます。
・通信の安定性
山間部やトンネルなど、電波が不安定な場所で通信が途切れてしまうと重要なデータが欠損し、システムの価値が半減します。移動範囲をくまなくカバーする信頼性の高い通信網が必須です。
・コストの最適化
映像を頻繁に送る車両と、位置情報をたまに送るだけの車両では、必要なデータ通信量が全く異なります。全車両に同じ大容量プランを適用すれば、莫大な無駄コストが発生します。車両一台一台の用途に合わせて、最適な料金プランを柔軟に選択できる仕組みが求められます。
・管理の効率性
数百台、数千台のSIMを管理するとなると、開通手続き、プラン変更、利用中断・再開、故障時の交換といった作業は膨大な手間になります。これらの作業をオンラインで一元的に、かつ効率的に行える管理ツールが不可欠です。
活用例①:業務効率化とコスト削減
・AIによる配送ルート最適化と動態管理
「ラストワンマイル問題」の解決策として注目されています。
AIがリアルタイムの交通情報や配送先の状況を予測し、新人ドライバーでもベテラン並みの効率で配送できるルートを自動生成してくれます。事務所においては全車両の現在地と作業状況を地図上で一元管理し、急な集荷依頼にも最も効率的な車両を割り当てることができます。これにより総走行距離を削減し、燃料費とドライバーの労働時間を直接的に削減します。
【ラストワンマイル問題とは?】
物流の最終拠点から消費者の手元に商品を届ける最後の区間において発生する、人手不足や再配達、コスト増加などの課題のことを総称した問題です。
・日報・月報の完全自動生成
走行データから、運転開始・終了時刻、走行距離、休憩時間、荷扱い時間などを自動で集計し、運転日報を自動作成します。これにより、ドライバーは一日の終わりに内容を確認するだけで済み、手書きや入力作業から解放されます。
活用例②:安全性の向上とコンプライアンス遵守
・AIドラレコによるインテリジェント安全運転支援
ドライブレコーダーが単なる記録装置ではなく、「コーチ」の役割を果たします。AIが脇見、車間距離不保持、一時停止といった危険運転の瞬間を映像から自動で検知し、ドライバーに即座に警告。また、歩行者検知も行い、事故の防止につなげます。
活用例③:未来の物流に向けた先進技術
・後続車無人隊列走行システム
経済産業省や国土交通省が主導して、高速道路における実証実験が進んでいます。
先頭車両のみドライバーが運転し、後続の複数車両が5G通信などを活用して無人で追従します。
これが実現すれば、一人のドライバーで3倍の輸送量を確保できる可能性もあり、人手不足問題の抜本的な解決策として大きな期待が寄せられています。
コネクテッドカーの実現にはロケットモバイル

コネクテッドカーを導入するにあたって特に費用面と通信エリアに対して不安を抱えている方が多いのかもしれません。
ロケットモバイルでは各々のニーズに合わせたSIMカードを使用することができます。
【ロケットモバイルのSIMの特徴】
・4キャリア対応
・幅広い通信容量からニーズに合わせたプラン選びが可能
・便利な専用管理ツールで一元管理が可能!
・固定IPと5Gのオプションが使用可能!
・4キャリア対応
広いエリアをカバーしているため、状況に合わせたキャリア選択が可能であり、データの取得に対する不便が少なくなります。
・幅広い通信容量
使用するデータ量に合わせたプラン選びが可能であり、超過後も200kbpsの通信が可能です。
また。「神プラン」においては月298円から利用が可能であるため、システム利用料を抑えることができます。
・専用管理ツール
契約した複数のSIMカードを一元で管理できるため業務の効率化を図れます。
・固定IPと5Gのオプション
固定IPオプションによるセキュリティリスクの軽減と5Gによる高速通信によって物流DXの推進が可能です。
ロケットモバイルについて詳しく知りたい!という方は以下のボタンからぜひご参照下さい。
まとめ
コネクテッドカーや5G、IoTは、物流業界が抱える人手不足やコスト高といった課題を、データに基づき解決する強力な道具です。物流の変革期において成功の鍵となるのは、壮大な計画よりもまず行動を起こすことです。自社の課題を洗い出し、数台の車両からでも試せるスモールスタートがおすすめです。私たちロケモバは、コネクテッドカーに不可欠なSIMの提供を通じ、お客様の次の一歩を全力でサポートします。