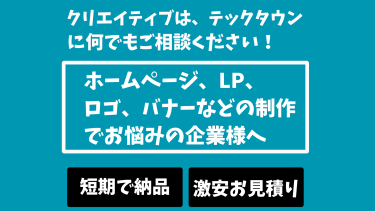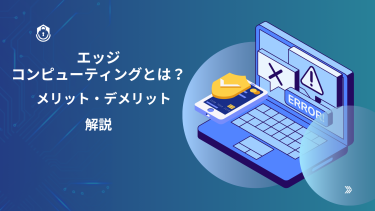「私物スマホを業務利用する”BYOD”って、実際どうなの?」
コスト削減や業務効率化の観点から、BYODを導入する企業が増えています。
しかし、実際には情報漏洩や端末管理の難しさといった課題も存在します。
本記事では、BYODの基本からメリット・デメリット、社用スマホとの違いを解説します。
加えて、業務用スマホの運用に関する注意点も詳しく紹介していきます。

BYODとは?

BYODとは「Bring Your Own Device」の略で、従業員が自分のスマートフォンやPCなどの私物端末を業務に活用する働き方を指します。
例えば、会社から指定された業務アプリやメール設定を、従業員自身がスマホにインストールして使用するケースが一般的です。
このように、会社が端末を支給する“社用スマホ”とは異なり、あくまで個人所有の端末を業務目的で併用するという点が特徴です。
なぜ注目されている?
BYODが注目される理由のひとつに、テレワークの普及が挙げられます。
近年では、外出先や自宅で業務を行うことが増え、柔軟に対応できる環境が求められています。
また、社用スマホを一人ひとりに支給するにはコストがかかります。
そのため、コスト削減や業務効率化を重視する企業にとっては魅力的な選択肢です。
BYODの導入はアメリカやイギリス、ドイツなどの欧米諸国を中心に進んでおり、2018年時点で既にアメリカでは23.3%、ドイツでは27.9%と高い普及率を示しています。
国内でも少しずつ浸透が進んでおり、2021年の情報処理推進機構(IPA)の調査では、小規模企業で40.7%、中小企業(101人以上の従業員)の16.1%がBYODを認めているという結果が出ています。
BYODを導入するメリット
BYODの導入を行うと、企業・従業員の双方にとって多くの利点があります。
- 端末コストが削減できる
- 働き方の柔軟性が広がる
- シャドーITの抑止に繋がる
順番に解説していきます。
端末コストが削減できる
社用スマホやPCを支給する場合、購入費だけではなく、通信費や保守費等の費用がかかります。
しかし、BYODであれば従業員がすでに持っている端末を活用できるため、企業は端末購入や維持の負担を大幅に軽減できます。
設備投資にかかる初期コストを抑えつつ、社内のデジタル化・業務のオンライン化をスムーズに進めやすくなるメリットがあります。
働き方の柔軟性が広がる
BYODを活用することで、自宅・外出先・出張先などでも、オフィスと同じように業務が行える環境が整います。
業務アプリやクラウドサービスに私物端末からアクセスできれば、リモートワーク等の多様な働き方にもスムーズに対応可能です。
また、急な出勤制限や災害時などの非常時にも、手持ちの端末で即時対応できるのはBYODならではの強みです。
シャドーITの抑止につながる
さらに、BYODの導入により、「シャドーIT」の発生も防ぐことができます。
「シャドーIT」とは、従業員が無断で私物端末や非承認アプリを業務に使うことです。
企業の管理外でのツールやサービスの使用は、セキュリティの侵害や情報漏洩のリスクが高まる要因になります。
BYODを許可するうえで、利用するアプリやアクセス範囲を企業側が管理する体制を構築すれば、より安全な運用が可能になります。
BYODのリスクとデメリット
一方で、BYODは、運用を誤るとトラブルの原因になることもあります。
導入前には、以下のようなリスクをしっかりと把握しておくことが大切です。
- 不正アクセスが起こる可能性がある
- 端末やデータの管理が難しい
- 労務管理が複雑になる
順番に解説していきます。
不正アクセスが起こる可能性がある
BYODで特に注意が必要であるのが、社外に機密情報が漏れるリスクです。
私物端末はあくまで従業員の個人所有のものです。そのため、企業側が完全に管理することはできません。
例えば、業務ファイルが個人のクラウドや写真アプリと自動同期されたり、端末の盗難でデータが閲覧される可能性があります。
特に顧客情報や契約書類などを扱う企業では、こうしたトラブルがそのまま信用問題に発展する可能性もあるため、慎重な対応が必要です。
端末やデータの管理が難しい
私物端末は、社内のIT部門等で一括管理するのが難しいという課題があります。
機種やOS、アプリの環境が統一されていない状況には、他にも問題点が挙げられます。
例えば、OSのバージョンによっては最新のセキュリティ規格が適用されていなかったり、業務アプリが正常に動作しなかったりすることもあります。
そのまま運用が続くと、脆弱性を突いたサイバー攻撃の対象になりやすくなります。
データの管理・運用・保守に影響を与える可能性があることに注意が必要です。
労務管理が複雑になる
私物端末を業務に使う場合、「勤務時間の線引き」があいまいになりやすくなります。
出社前にスマホで業務メールを確認したり、退勤後にメッセージに返信したりすることが日常化している場合などが例に挙げられます。
このような場合、労働時間の管理や残業代の取り扱いが不明確になることがあります。
また、端末の通信費や修理費等の管理についても同様です。
社用スマホ(法人スマホ)との違い

BYODと社用スマホは、運用方法や管理体制、端末の取り扱いや管理方法等に大きな違いがあります。
ここでは、BYODと社用スマホの主な違いを比較しながら、それぞれの利点や注意点をもう一度整理していきます。
導入・運用にかかる費用
端末の導入・運用費用は、コスト管理をするうえで確認しておきたいポイントです。
こちらは、端末管理やリスク対応体制の違いをまとめた比較表です。
| 項目 | BYOD | 社用スマホ |
|---|
| 初期費用 | ほぼゼロ(既存の端末を使用) | 端末購入・回線契約などが必要 |
| 通信費 | 基本的に個人負担 or 一部補助 | 会社が契約・負担 |
| 運用コスト | 管理負担は軽いが、セキュリティ 対策費が必要な場合も | 管理・保守に定期的なコストが 発生 |
BYODは社用スマホと比べて導入ハードルが低い点が魅力です。
ただし、通信費の補助やセキュリティ対策が不十分である場合、従業員側に負担が偏るリスクもあります。そのため、運用ルールの設計をきちんと行うことが重要です。
セキュリティ管理方法
安心して業務に使うためには、セキュリティ管理方法の違いも押さえておくことが大切です。
| 項目 | BYOD | 社用スマホ |
|---|
| 管理のしやすさ | 端末の統一管理が難しい | 端末を一元管理しやすい |
| リスク対応 | 紛失・不正アクセス時の対応が 困難になりやすい | 遠隔ロック・データ消去などの 手段が取りやすい |
| セキュリティ基準 | 個々の端末設定に依存 | 会社が一律で設定・運用可能 |
端末の管理においては、BYODでもMDM(モバイルデバイス管理ツール)の導入により、一定の管理は可能ですが、あくまで最低限の管理体制を補完する目的での使用になります。
端末の機種や設定がバラバラであること、従業員の同意が必要なことから、社用スマホのような一括制御は難しいのが実情です。
従業員の使いやすさ
業務効率や従業員満足度に関わる部分として、操作性や扱い方も確認しておきましょう。
| 項目 | BYOD | 社用スマホ |
|---|
| 操作のしやすさ | 使い慣れた端末で業務にすぐ 入れる | 慣れるまでに時間がかかる場合がある |
| 公私の切り分け | プライベートと業務の境界が 曖昧になりやすい | 明確に分けられるため、 オン・オフの切り替えがしやすい |
BYODの場合、操作に慣れている分、業務にスムーズに入ることができます。
その一方で、公私の区別や管理方法に配慮が求められるケースが少なくありません。
社用スマホは業務に特化した端末として運用できるため、情報の管理やプライバシー配慮の面でも一定の安心感があります。
導入前に必要な準備
BYODは、柔軟でコスト面でもメリットがありますが、導入にあたっては事前に決めておくべきルールや準備事項がいくつかあります。
こうした準備を後回しにしてしまうと、情報漏洩や従業員とのトラブルにつながる可能性もあるため、導入前のひと手間がとても重要です。
ここでは、BYODを導入する際に企業側で確認・整理しておきたいポイントを紹介します。
BYODの利用範囲を明確にしておく
まずは、BYODをどこまで認めるのか、どの業務に利用を限定するのかを明確にします。
たとえば、営業や出張の多い職種のみに限定する場合や、メールやチャットなど特定の業務だけに活用を許可する場合などが挙げられます。
また、自社のクラウドシステムやVPNへの接続を認めるかどうかといった点も、事前に判断が必要です。
こうしたルールをあらかじめ決めておくことで、従業員の混乱やトラブルを未然に防ぐことができます。
セキュリティポリシーの整備を行う
BYOD導入において最も重要なのが、セキュリティに関する社内ルールの整備です。
たとえば、ウイルス対策ソフトの導入や、パスコードロック・生体認証の設定を必須にすることなどが挙げられます。
また、データの保存先やwi-fi利用等、端末の利用方法に関してもルールを設けておくと安心です。
MDMなどの端末管理ツールの導入を行う
私物端末を業務利用する場合、セキュリティリスクが高くなる可能性があります。
端末に業務用アプリを入れる際は、MDM(端末管理ツール)を併用して、端末制御を行うことが望ましいです。
MDMの導入を行うことで、業務データの削除やアプリの利用制限等が可能になります。
万が一の紛失時に、端末に保存された業務データを保護する目的などに活用できます。
ただし、あくまで私物端末である以上、こうしたツールの導入には従業員の同意が不可欠です。
利用規約・運用ルールの整備
BYODを導入するにあたっては、企業と従業員の間であらかじめ取り決めておくべきルールが数多く存在します。
特に、端末のトラブルや利用終了時に関する責任の所在については確認が必要です。
たとえば、業務中に私物端末が破損した場合の費用負担は誰がするのか、業務利用にかかる通信費は会社が一部補助するのかといったことが含まれます。
さらに、退職時のデータの削除手順やアカウントの無効化方法なども対応フローに関しても事前に整備しておく必要があります。
業務用スマホを正しく運用するために

BYODでも社用スマホでも、端末を業務に活用する以上、日常的な運用管理の工夫が重要になります。導入だけではなく、運用時の管理体制をしっかり整備することも大切です。
ここでは、トラブルを防ぎながら業務効率やセキュリティの強度を維持するためのポイントを紹介していきます。
定期的なセキュリティチェック
業務用スマホを安全に運用していくには、端末の状態を定期的に確認し、セキュリティリスクを未然に防ぐことが欠かせません。
OSやアプリのアップデートが滞っていないか、ウイルス対策ソフトが正しく機能しているかなど、基本的な確認項目を定期的にチェックする仕組みが重要です。
また、BYODのように私物端末を活用する場合は、企業側が一括で管理できる仕組みを導入することも有効です。
なかでも、モバイルデバイス管理(MDM)ツールは、多くの企業で導入が進んでおり、以下のような管理機能を備えています。

また、次のようなツールを活用すれば、社外利用やアクセス面の不安も解消できます。
VPN
インターネット上に暗号化された専用の通信経路を作ることで、第三者に情報を盗み見られずに安全な通信が可能になります。社外から社内ネットワークへアクセスする際も、機密データのやりとりも安全です。
リモートアクセスツール
自宅や外出先の端末から、社内のPCや業務システムに安全にアクセスできるツールです。
重要なファイルをローカル端末に保存せず、社内の環境だけで業務を完結させられるため、情報漏洩リスクの低減につながります。
クライエント証明書
端末やユーザーが正規の利用者であることを証明する電子証明書型の認証手段です。
あらかじめ許可された端末だけがシステムに接続できるよう制御できるため、不正アクセスやシャドーITの防止に効果的です。
ウイルス対策ソフト
マルウェアや不正プログラムをリアルタイムで検出し、ブロックするソフトです。
個々のデバイスに導入することで、巧妙化するサイバー攻撃から業務データを保護します。
まとめ
スマートフォンやタブレットを業務に取り入れることは、働き方の柔軟性を高めるうえで、今やごく当たり前になっています。
BYODもまた、うまく活用すれば負担を減らしつつ、業務をスムーズに進める手段にもなり得ます。
導入時には、コストや柔軟性といった表面的なメリットにとどまらず、運用面の整備や社内での管理をしっかりと行うことが大切です。
「使いやすく、安心して利用できる」といった視点で端末の活用を進めていきましょう!

BYODの通信・セキュリティに不安はありませんか?
私用端末の業務利用では、通信環境やセキュリティ設計が重要です。
弊社では、モバイル通信のプロが無料でご相談を承っています。
「社員のスマホを安全に使いたい」「通信コストを最適化したい」など、
BYOD運用にまつわるお悩み、ぜひご相談ください!