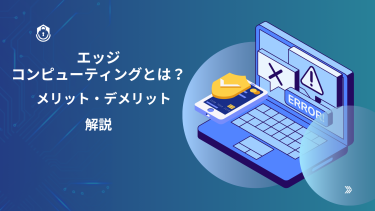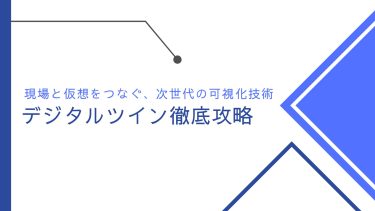IoT(Internet of Things)の普及が進んでいる現代において、私たちの身の回りでは膨大な数のデバイスがネットワークに接続され、様々な情報がやり取りされています。
そして、そのようなIoT時代の社会を支える基盤となる通信技術が「LPWA」です。
本記事では、LPWAの基礎知識から5Gとの違い、活用方法から今後の展望までを徹底解説します。

LPWAとは?

LPWAは「Low Power Wide Area」の略で、省電力かつ広範囲に通信できる無線通信技術の総称です。
LPWAN(Low Power Wide Area Network)とも呼称され、従来のWi-FiやBluetoothと比べてはるかに広いエリア(数km~数十km)をカバーできます。
加えてバッテリー消費が極めて少ないため、長時間での稼働が求められるIoTデバイスには最適な通信手段であると言えます。
LPWAの主な特徴
LPWAには以下のような特徴があります。
1.広範囲通信
LPWAを用いると、数km~数十kmの長距離通信が可能です。
これは、通信距離が最大でも数十~数百m程度の従来のWi-FiやBluetoothなどと比較し、遥かに広い通信エリアをカバーできることを意味します。
この特徴によって、特に都市部だけでなく、農地・山間部・工場地帯などのインフラが整っていない場所でも通信が可能であるため、スマート農業や遠隔監視、防災システムなどの様々なIoT分野での活用が期待されています。
2.省電力
LPWAは、通信に必要な消費電力が少ないことも大きな特徴です。
LPWAでは、できる限り単純化した通信方式を採用しているため、無駄な電力の消費を大幅に抑えることができます。
そのため、電源の確保が難しい場所や、頻繁なメンテナンスが困難な環境で積極的に活用されており、場合によっては乾電池1本でIoTデバイスを数年間運用することも可能です。
3.低コスト
LPWAを用いる場合、通信費用や機器のコストが安いという点も大きな特徴の一つです。
通信費用に着目すると、LTEや3Gを用いた通信を行う場合には、最低でも300~数千円程度の月額費用がかかりますが、LPWAの場合には通信費用は10~100円/月程度に抑えられており、圧倒的に安価です。
また、機器のコストに関しても、LTEや3G対応の通信モジュールは一般的に数千円の費用が掛かり、センサー等と組み合わせた完成品の場合には数万円の費用が掛かります。
一方でLPWAの通信モジュールの費用は2ドル程度で、完成品でも2,000円程度で購入できます。
4.低速
他の通信方式と比較し、低速な通信を行うという点もLPWAの特徴の一つです。
Wi-FiやBluetoothといった従来の通信方式では、高速な通信が利用可能ですが、他方で長距離通信が難しい・消費電力が大きくなる等のデメリットが存在します。
一方のLPWAでは、通信速度を低速に抑えることで、広範囲での通信や省電力性を実現しています。
そのため、データをリアルタイムで転送する必要のある自動運転であったり、大容量データの転送が必要な動画編集などの用途には不向きなLPWAですが、専ら小さなデータを遠距離でやり取りすることが多いIoT用途においては、非常に理にかなった通信技術であると言えます。
各通信方式とLPWAの違い(消費電力・通信速度、通信距離の比較)

画像出典:株式会社コンテック(https://www.contec.com/jp/support/blog/2022/220715_lpwa-iot/)
5.同時接続数が多い
LPWAでは、多数のIoTデバイスを同時に接続できるという、IoT用途において欠かせない特徴が備えられています。
5GやLTE通信においてもデバイスを複数台同時に接続することは可能ですが、これらの方式では各デバイスの通信の安定性が低下してしまうというデメリットが存在します。
一方、LPWA(特にLoRaWAN)では1つのゲートウェイあたり約100台のエンドデバイスを同時に安定して接続・運用できることが確認されています。
また、一部のLPWA機器では同時通信チャンネル数が8~16程度に制限される場合がありますが、これは「同時に通信できる数」であるため、通信タイミングをずらすことで実質的な同時接続台数を増やすことができます。
このように、LPWAではIoT用途における「多数のデバイスを同時に安定運用する」というニーズを満たす特徴を有しています。
【LoRaWANとは】
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)はLPWAに分類される通信規格の一つで、920MHz帯などのライセンス不要周波数を使用し、最大10㎞程度の通信距離を実現しています。
似たような概念として【LoRa】が存在しますが、こちらは変調方式のことを指す単語であり、LoRaWANはこれを利用した通信プロトコルであるため、両者は異なる概念です。
LPWAと5Gの違い
先程のセクションで解説した通り、「低速広範囲通信」という特徴を持つLPWAですが、高速通信の代表格である5Gとの間には様々な違いが存在します。
LPWAと5Gの違いは、各項目ごとに以下の通りとなっています。
| 項目 | LPWA | 5G |
|---|---|---|
| 最大通信距離 | 20㎞~50㎞ | 数百m~1㎞ |
| 消費電力 | 極めて低い | 高い |
| 最大通信速度 | 低速(250kbps、LoRa方式) | 高速(上り480Mbps/下り10~20Gbps) |
| 同時接続数 | 多数(約100台/ゲートウェイ、実証済み) | 非常に多数(約100万台/㎢、ただし理論上) |
| 主な用途 | IoT用途(遠隔監視、センサー等) | 高速通信を要するもの(映像通信、AR/VR、自動運転等) |
| コスト | 低コスト | 高コスト |
| 免許 | 不要な規格も存在 | 必須(キャリア) |
これらの違いから、LPWAと5Gは明確な競合関係ではなく、互いに使用場面が異なる補完関係にあると言えます。
LPWAの主な種類と特徴
LPWAに分類される通信規格は、それぞれ利用する周波数帯や運用携帯によって「ライセンス系(免許必須)」と「アンライセンス系(免許不要)」の2種類に大別されます。
ライセンス系は「セルラー系」とも呼称され、通信を行うためには無線局免許状が必要となりますが、アンライセンス系では必要ないため比較的導入が容易です。
ライセンス系・アンライセンス系それぞれの通信規格の種類は以下の通りです。
ライセンス系
・NB-IoT
NB-IoT(NarrowBand IoT)は、ライセンス系の通信規格の中でも特に人気のある通信方式です。
既存のLTEのリソースを用いつつ、180㎑という狭い帯域幅で通信を行うため、既存のLTE設備を利用可能な他、ネットワークとの干渉が起こりづらいという強みがあります。
国内キャリアではSoftBankと楽天モバイルが、NB-IoTを利用できるプランを提供しています。
特徴
- LTEの既存ネットワークを拡張し利用するため、設備投資を最小限に抑えられる
- 180㎑の帯域幅で通信を行うため、他のネットワークと干渉しづらい
- 通信速度は最大250kbps
- 最大通信距離は約20㎞
・LTE-M
LTE-M(LTE Cat-M1)は、LTE網を用いた中速通信が可能なライセンス系通信規格です。
NB-IoTと同様に、通信には既存のLTEのリソースを用いるため、設備投資を最小限に抑えることが可能です。
また、用いる帯域幅は1.4㎒であるため、NB-IoTと同様に既存のネットワークとの干渉を避けた運用が可能なほか、NB-IoTと比較してより高速な通信が利用可能です。
特徴
- LTEの既存ネットワークを拡張し利用するため、設備投資を最小限に抑えられる
- 1.4㎒の帯域幅で通信を行うため、他のネットワークと干渉しづらい
- 通信中の移動が可能(複数の基地局を跨いだ通信が可能)
- 通信速度は最大1Mbps
- 最大通信距離は約10㎞
| 項目 | NB-IoT | LTE-M |
|---|---|---|
| 種別 | ライセンス系 | ライセンス系 |
| 帯域幅 | 180㎑ | 1.4㎒ |
| 基地局を跨いだ通信 (ハンドオーバー) | × | 〇 |
| 通信速度 | 最大250kbps | 最大1Mbps |
| 最大通信距離 | 約20㎞ | 約10㎞ |
法人向け格安SIMサービスのロケットモバイルでは、LTE-MのほかにLTE Cat.1に対応したプランを提供しており、ライセンス系LPWAを格安で利用することが可能です。
詳しい提供プラン名は、以下のサイトをご参照下さい。↓
【法人】ロケットモバイルはLTE-Mやcat.1に対応していますか? – ロケットモバイル ヘルプセンター(FAQ)
アンライセンス系
・LoRaWAN
LoRaWAN(Low Power Wide Area Network)は、広域かつ低消費電力な通信に強みを持つアンライセンス系通信規格です。
LoRa(Long Range)という変調方式をベースに構成されており、わずかな電力で数㎞〜数十㎞の通信が可能なことから、スマートメーターや農業センサー、環境モニタリングなど、定期的に少量のデータを送るIoT用途に最適です。
日本国内では、920MHz帯の免許不要周波数を利用しており、LoRaWANゲートウェイを設置することで、独自のIoTネットワークを構築することも可能です。
特徴
- 周波数帯は920㎒帯を利用し、免許不要で利用可能
- センシング用途など、低頻度・小容量の通信に最適
- 最大通信距離は15㎞~20㎞程度
- 通信速度は最大50kbps程度
・SIGFOX
SIGFOXは、超低速・超低電力性に強みを持つアンライセンス系通信規格です。
通信に用いる周波数帯はLoRaWANと同様920㎒帯を利用し、ごく少量のデータを長距離で送受信できるのが大きな特徴です。
また、通信帯域には独自の「UNB(Ultra Narrow Band、超狭帯域)」を採用しており、他のネットワークとの干渉が少ない点も特徴です。
加えて、LoRaWANではゲートウェイを自前で設置して使うのに対して、SIGFOXでは通信インフラがすでに事業者によって整備されており、ユーザーはネットワークに接続するだけで手軽に利用することが可能です。
特徴
- 周波数帯は920㎒帯を利用し、免許不要で利用可能
- UNBを採用しており、他ネットワークとの干渉が少ない
- 消費電力が非常に少なく、数年~10年単位の長期運用が可能
- 最大通信距離は50㎞程度
- 通信速度は最大100bps程度
- 通信回数には上り140回/日、下り4回/日の制限あり
・ELTRES
ELTRESは、ソニーが開発した高速移動体通信に強みを持つアンライセンス系通信規格です。
独自の通信技術の採用により、時速100㎞以上で移動している最中であっても通信を行うことが可能なほか、高い受信感度と耐干渉性も実現しています。
現在、ELTRESは日本国内を中心にエリア展開されており、ELTRES通信を利用できる商用ネットワークも提供されています。
特徴
- 周波数帯は920㎒帯を利用し、免許不要で利用可能
- 高速移動中(時速100㎞以上)でも通信可能
- 高精度な位置情報(GNSS)と連携可能
- 高い受信感度・耐干渉性を実現
- 最大通信距離は100㎞
- 通信速度は最大100bps程度
・ZETA
ZETAは、メッシュネットワークの構成が可能であるという点に強みを持つアンライセンス系通信規格です。
メッシュネットワークとは、ネットワークに存在する複数の端末が相互に接続しある構造を持つネットワークのことです。
この特徴により、ZETAではネットワークに存在する各IoT端末が中継器のような役割を果たし、通信範囲を拡張することが可能です。
また、メッシュネットワークを利用することで、センサー間の連携や電波の届きにくい建物内での通信がしやすいといったメリットもあります。
ZETAはLPWAの中では比較的新しい規格ですが、その通信の柔軟性が評価され、スマートビル、スマート農業、工場内のモニタリング等の様々な用途での活用が進んでいます。
特徴
- 周波数帯は920㎒帯を利用し、免許不要で利用可能
- メッシュネットワーク構成に対応
- 通信帯域は2㎑のUNB(超狭帯域)を利用し、耐干渉性が高い
- 最大通信距離は10㎞程度(メッシュネットワークを用いた中継により拡張可能)
- 通信速度は最大300bps~2.4kbps程度(用いるプロトコルによって変動)
| 項目 | LoRaWAN | SIGFOX | ELTRES | ZETA |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | アンライセンス系 | アンライセンス系 | アンライセンス系 | アンライセンス系 |
| 周波数帯 | 920㎒ | 920㎒ | 920㎒ | 920㎒ |
| 主な特徴 | 低頻度・低用量の通信に最適 | 超低速・超低電力通信 | 高速移動体通信 高い受信感度・耐干渉性 | メッシュネットワークを構成可能 |
| 通信速度 | 最大50kbps | 最大100kbps | 最大100kbps | 最大300bps~2.4kbps |
| 最大通信距離 | 約15~20㎞ | 約50㎞ | 約100㎞ | 約10㎞ |
LPWAの活用方法

ここまで、LPWAの基本情報や5Gとの違い、規格の種類について解説してきましたが、では実際にLPWAはどのような場面で活用されているのでしょうか?
以下で、省電力・長距離・低コストといった特徴を持つLPWAの代表的な活用方法について紹介していきます。
スマートメーター・検針
ガス・水道・電機などのメーターに、LPWA対応の通信端末を導入することで、遠隔から自動検針を行うことが可能になります。
実地に赴いての調査が不要となるので、業務の効率化はもちろん、誤った検針を防止したり、送信データを通してリアルタイムでの利用状況の監視が可能になるなど、様々なメリットが生まれます。
工場・インフラ監視
工場内の設備やインフラの監視においても、LPWAは広く用いられています。
工場内の配管やセンサー、橋梁やダムなどのインフラ設備にLPWA対応の通信端末を導入することで、振動・温度・劣化などの状態を遠隔監視できます。
特に、LPWA端末では広範囲かつ長期間の監視が可能であるため、設備の異常を早期に察知し、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
農業分野
農業分野においては、土壌の水分量・気温・湿度・CO2濃度などの環境データを自動収集し、農作物の栽培環境の最適化や効率化を図る「スマート農業」の取り組みにおいて、LPWAは用いられています。
スマート農業では環境監視以外にも、センサーによる盗難防止であったり、水田の給水・排水の自動制御や遠隔操作等の様々な取り組みが行われていますが、これらの用途においてもLPWAは広く活用されています。
これらのスマート農業の取り組みでは、監視機器との通信を数年単位ので安定して行う必要があり、また農業の中心地である山間部では、都市部と比較し通信設備が整っていないことが多いのが現状です。
こうした背景から、省電力・広範囲通信が可能という特徴を持つLPWAは、農業分野と特に相性が良いと言えます。
物流・トラッキング
物流・トラッキング分野においては、輸送中の荷物や車両の位置情報や状態(温度・開封検知など)をリアルタイムで把握する用途でLPWAが用いられています。
LPWAでは小型で省電力なデバイスを使って長時間・長距離のトラッキングが可能なため、特にコールドチェーンや貴重品輸送などの分野で利用が進んでいます。
移動体との通信が前提となるこれらの用途においては、複数の基地局を跨いだ通信が可能なLTE-Mや、高速移動体通信が可能なELTRESが用いられることが多いです。
環境モニタリング
環境モニタリングの用途においても、LPWAの利用は非常に有効であると言えます。
河川の水位、空気中の微粒子(PM 2.5)、騒音、照度などの環境データを定点観測する用途に最適です。通信設備が整っておらず、電源確保が難しいような場所でも、省電力・広範囲通信が可能なLPWA機器を用いれば、完全自立型のモニタリングシステムが構築可能です。
防災・見守り
長期間にわたる安定した通信環境が必要な防災・見守り用途においても、LPWAは活用されています。
災害の危険性が高い山間部や人が常駐しない地域にセンサーを設置し、LPWA機器を通した遠隔監視を行うことで、土砂崩れの兆候や河川の増水、異常気象の情報を早期に検知することが可能です。
また、見回りが困難な場所での安否確認やアラート送信にも活用されており、LPWAは災害時の迅速な初動対応を支援しています。
今後の展望と課題

社会全体でのIoTのニーズの拡大に伴い、LPWAの需要は今後ますます高まると予想されます。
特に、都市部だけでなく山間部や離島などの、従来の通信インフラが整備されていない場所での活用が期待されています。
また、今後はLPWAと5Gのハイブリッド運用や、AI・ビッグデータとの連携による新しい活用方法の創出も進んでいくでしょう。
LPWAの活用が進んでいくことが予想される一方で、LPWAには規格間の互換性やセキュリティといった課題が残されていることも事実です。
LPWAを用いたIoTの活用がより普及していくためには、これらの課題を乗り越える必要があると言えるでしょう。
まとめ
今回の記事では、通信技術の一つであるLPWAについて、基礎知識から主な活用方法まで網羅的に解説しました。
IoT社会の発展に伴い、あらゆるモノがネットワークにつながる時代が到来しています。
その中で、LPWAは「省電力」「広範囲通信」「低コスト」等の特長を活かし、スマートメーター、インフラ監視、農業、物流、防災などの様々な分野で欠かせない存在となっています。
今後、LPWAはさらに多様な活用が期待される一方、規格の標準化やセキュリティ対策など、乗り越えるべき課題も残されています。
本記事を参考に、LPWAの特性を正しく理解し、自社やプロジェクトに最適な通信技術の選定・活用を進めていただければ幸いです。

📡 IoTやLPWAの通信選び、迷っていませんか?
IoT導入時に重要なのが通信方式の最適化。LPWA(Cat.1、LTE-Mなど)は用途により最適な選び方が異なります。
弊社では法人向けに通信相談を無料で受付中です。
「Cat.M1とCat.1の違いって?」「LPWAを導入するならどのSIMがいい?」など、
具体的な導入シーンに合わせたご提案が可能です。お気軽にご相談ください!